 |
|
NAFとは
ごあいさつ
活動報告
保護区紹介
ご寄附・お問合せ ギャラリー トピックス 関連書籍 リンク |
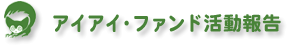 【No.11 平成15年6月】 島代表が山口県立下関西高校で講演を行いました (以下は山口県立下関西高校で6月6日に行った講演の原稿です)
日本アイアイ・ファンド代表、マダガスカルアイアイ・ファンド名誉会長 私は毎日、物を書いておりますから、これが売れれば物書き、作家、自由業と言えるのですが、私としては欧米には時々いる「独立研究者」と考えていて、動物学者あるいは霊長類学者と自称しています。 マダガスカル国政府からは、第五等勲章にあたる「シュヴァリエ Chevalier」を授与されています。英語では武士道にあたる騎士道が「シヴァリー Chivalry」ですから、イギリスなら「ナイト」称号ですが、もともと彦島の魚屋の息子ですから、無論貴族であるはずもなく、ナイトと言ってもアンモナイトと同じようなものというわけです(ちなみにこれがマダガスカルのアンモナイト)。 ■ざっとした私の経歴 西高に入ったのは1961年で、空前のベビーブームと言われた年の一年前のため、定員不足で受験者全員合格という幸運な人生のスタートを切りました。だから、同級生には、当然のことながら、普通なら西高には入っていなかったという劣等生もいたわけですが、それでも西高を選ぶという気概がどんな青年を生むかという実例を見てきました。人は学力だけじゃあないのです。 ともあれ、学力的に問題のなかった私は、東大へ、理学部へ、大学院へと進み、末は東大教授の道を順調に歩んでいたはずなのですが、三十歳の時、財団法人設立という離れ業に出ます。 あれ、そこで三十というのはずいぶん回り道があったんじゃないのか、という疑問は無視しましょう。二十五歳でニホンザルの研究をはじめ、二十七歳で「雑誌にほんざるー日本の自然と日本人」を編集長として創刊し、二十八歳の時にイリオモテヤマネコの世界初の映像撮影に成功していましたから、なんとなく順調だったんだなと素直に考えてください。(それでも、この二十代の経歴に疑問がある方は、お申し出ください。個別に説明したいと思います) ■専門家たち もっとも人生のわずかな狂いのそもそもは、あの教室にあったかもしれません。東大理学部と言っても、そこは人類学教室というところで、生物学科の劣等生の集まりで、東大の赤門はいちおう入るのですが、そのまま右手に塀に沿って隅のほうへ行くと、古色蒼然たる三階建ての建物があり、教室はその三階の片隅にひっそりと隠れていました。廊下には縄文土器や古墳から出た埴輪、ポリネシアの槍やインカのミイラの首などが並べられて、夜中に歩くのはそうとう勇気が必要な場所でしたね。 私の指導教官は、「生態人類学の祖」と自らを呼ぶ渡辺仁さんで、彼は最晩年になっても「アメリカ探検家協会」から会員として認められたことを誇りにするような人でした。 「北極点に歩いて到達した、あの植村直巳のいた協会に推薦で、ぼくは会員になった。君。ぼくの称号は『知の冒険者』だそうだよ」と。 サルの研究の指導者は、後に国際霊長類学会会長となった西田利貞さんでした。学生を置いて一人でどんどん歩いていってしまう西田さんも衝撃的でした。 「人の後から歩いているとな、動物は見えへんで。最初の人間だけや、野生の動物を見られるのは」というのが、西田さんの口癖でしたが、そのとおりの人生を彼は歩いています。彼の創始したチンパンジーのためのタンザニアのマハレ国立公園は161,300ヘクタールで、今年マダガスカルに私たちが作ったアンジアマンギラーナ監視森林14,380ヘクタールの十倍の面積があります。なかなかに師を越すというのは、たいへんなのです。 植物学の指導者として農学部の高杉欣一さんに出会ったことは、実に大きな経験でした。彼は生涯助手を貫いた人ですが、その先生もえらい人で、サルが葉も芽もみんな食べてしまった茎だけを持っていっても、「明日まで待ってね」と丁寧に調べて、ついに名前を教えてくれるのです。私の同僚で今では霊長類研究所の教授になった男がいますが、その同じ標本を見て「根から花から葉までそろって植物の種は同定できるんだ。根も葉もないものが同定できるか?」と怒ったものですが、プロというものは人間のできが違います。 ■野生とは何か 千葉県に高宕山というサルの天然記念物指定地域があって、そこが西田さんのフィールドでした。私はそこで初めて野生のサルに出会いました。これは衝撃的な出会いでした。これが野生というものの輝きか、と。動物園のサルとはまったく別の姿でした。 この房総丘陵で風雨にかかわらずサルを追いかけながら、野生とは何か?ということを追求したことは私の人生にとって大きかったのだと、思うことがあります。それは雨の中でもサルたちが平気なのは、なぜか?というような、学問とはいえないような疑問を今までひきずって、人間はなぜ裸なのか、と考えています。 野生の動物というものは、人間とは根底から違う。それは生きている原理そのものが違うのだ、という感覚そのものです。これは現在書いている人間進化に関する本をまとめる上で根本的な視点を確認させてくれることになりました。 台風で崖上の小屋が飛ばされたので、崖下の洞窟に住んでいましたが、そこで修行中の空手家といっしょにしばらく暮らしたり、「一日一回は冒険をしよう」ととうてい通れないと思われる崖を、命がけで登ったり降りたりしたのもこのころです。今その崖に行って見ると、とんでもないやつだったんだなあ、とつくづく思います。 まあ、「人間野生」というようなものだったわけですね。それは私にとっては、専門家になるための修行時代だったなあ、と思っています。 ■財団設立と国際協力事業団専門家 財団法人日本野生生物研究センターの設立は、私が三十歳の時ですから、二十代の決算だったといえます。 その財団法人にいるとき、TBSの「わくわく動物ランド」という番組が始まり、その立ち上げから「ブレン・グループ」として参加しました。これは長寿番組で、その最初の形を保って、現在も「動物奇想天外」という番組名になって続いています。その番組に出ている千石正一さんは学生時代から私たちのグループにいたので「先刻承知」の人です(あ、ここは駄洒落ですから、笑うか、拍手するか、どっちかですよ) さて私のほうは、その番組の取材で1983年にマダガスカルにアイアイを探して行くことになりました。翌年アイアイを見つけ、世界初のアイアイの映像をとり、その最初の論文を1988年に発表して、その年からはマダガスカルにアイアイの研究のために連続して行くようになりました。財団を設立以来10年間がたっていましたが、ここで辞職し、東大に研究生として戻り博士論文を準備していました。その間に、西田さんが京都大学に移ったので、京大で理学博士をもらいました。 このころ外務省の外郭団体の国際協力事業団とから、専門家としてマダガスカルに派遣されることになりました。「霊長類学の指導」というたいそうな名目で、1990年に三ヶ月、1992年からと1998年からそれぞれ3年間ずつ、最近10年ほどの間に6年以上マダガスカルで生活をしました。2001年には上野動物園にアイアイやマダガスカルトキなどを持ってきました。去年アイアイ・ファンドを設立し、今年アイアイの保護区がマダガスカルに新設されましたので、毎年マダガスカルに行くことになったわけです。今年は来週から8月末までと11月ですね。 こうしてみると実に明瞭な履歴で、サル関係とマダガスカルという観点からはまったく一貫した人生であると言えます。実は、さまざまな偶然の折りなす網目でこうなっただけなのですが。 ■マダガスカルとは 前置きが長くなりました。まずはスライドを見てもらいましょう。マダガスカルという世界とその動物たちです。(あれは何かとずっと思っている人がいると思いますが、)私の前においてあるのは、マダガスカルの石です。水晶ですが、少し暗い色なので煙水晶と呼ばれ、英語ではスモーキー・クオーツ、フランス語ではクオルツ・フメといいます。光があたると金色を帯びる暗い結晶の中に白い煙か、微小な天の川のようなものが見えます。まあ、マダガスカルの代表的な石の一つです。マダガスカルは石の国でもありますが、その話は今回はしません。長くなりますからね。 マダガスカルはその国土面積が日本列島全体の1.6倍あります。59万平方キロ、ああ、ノートはいいです。試験には出ないでしょうからね。ただ、世界第四位の島ということでは覚えておいたほうがいいかも知れません。グリーンランド、ボルネオ、ニューギニアの次です。そこまで言っても、「九州と比べたらどうか?彦島よりはちょっとは大きいか?」という人々は後を絶ちません。ちょっとは大きいくらいです。マダガスカルは九州の面積の十六倍あります。 マダガスカルは南半球にあるので、これから冬です。しかし、熱帯ですから、一年中気温が高いのです。しかし、首都アンタナナリヴは標高1300メートルの高原にありますから、実にさわやかな気候です。なにしろ年間平均気温17度で、月平均気温が一月で最高の二十度、七月に最低の十三度、一年中ほとんど差がありません。また、適度の雨が降り、一般には湿度の低いところです。 つまり、世界でもっとも気候のいい場所のひとつがこのマダガスカルの高原地帯なのです。ここは人間がもっとも遅くなって到達した場所でもあり、今から二千年前までは、まったく無人地帯、野生の動物たちの天国だったところです。その天国とはどれくらい続いた天国だったのか?千年、二千年、そんなものではない。アフリカ大陸から離れたのは一億六千万年前と言われています。それいらい、ほかの大陸と無関係に、この島独自の生命系が作られてきたわけです。 もちろん、六千五百万年前に恐竜の世界的絶滅があったので、マダガスカルの恐竜もアンモナイトも全部絶滅しています。しかし、どうも恐竜の時代からの生き残りがそこここに生きているのが、マダガスカルです。 (ここからスライド) アンタナナリヴです。ちょっと舌をかみそうですが、タナナが町という意味なので、ナが重なるわけですな。町の中心部のアヌシ湖と崖の上の女王宮殿の風景です。マダガスカルの人種は何かとか、女王がなぜいるのか、とか、お前はその女王と親しいのかとか、いろいろな疑問はともかく。公園に遊びにきていて、私が親しくなったマダガスカル人女性と男性です。 恐竜時代からの生き残りではないか、という疑いがもっとも濃いのはヘビの仲間です。たとえば、ボア。アフリカにはニシキヘビがいますが、南アメリカとマダガスカルにはボアがいます。彼らは恐竜の時代に生きていて、大陸が分かれていったので、マダガスカルと南米に残ったというわけです。 たぶん、カメレオンもそうでしょう。現在世界のカメレオンの半分とも六割とも言われるほどのカメレオンがマダガスカルにいますが、その最大種から最小種までがマダガスカルにいて、私のマダガスカルの家の庭にもおります。このカメレオンは、マダガスカルが原産地でそこから世界に広がったことが最近分かりました。これはヌシ・マンガベニジイロカメレオンと私が勝手に名前をつけて呼んでいたのですが、そのまま和名になりました。それから世界最小のヒメカメレオン、乾燥地帯のカメレオン。痩せていますね。アンタナナリヴの我が家にもカメレオンはいます。太っていますね。我が家のばあいは栄養がいいのです。これはマダガスカル高地のどこにでもいる、日本でいえばスズメのようなふつうのカメレオンです。 同じように、マダガスカルはバオバブの原産地でしょう。アフリカには一種、オーストラリアには二種しかありませんが、マダガスカルには七種があります。 このアフリカバオバブはマダガスカルとアフリカに共通種です。ねっこがさかさまになったような、という「星の王子様」に出てくるバオバブです。乾燥地帯の水辺に生えるバオバブはグランディディエバオバブで、有名なバオバブの並木があります。 マダガスカルはインド洋に沈んだレムリア大陸の破片だという説がありますが、このレムリアはマダガスカルの原猿類のラテン語名、レムールを語源としています。このサルたちもマダガスカルが原産地かどうかは説の分かれるところですが、その科の数は世界の霊長類の半分を占めています。真猿類はメガネザルを含めても七科で、マダガスカルの原猿類も七科である。 マダガスカル中央部は高原地帯ですが、今では日本全土に匹敵する面積が焼け野原という状態で、川沿いの湿地を水田に、斜面をマニョク(芋)などの栽培に、草原を牛の放牧にわずかに使っているだけです。地質的におもしろい地形ですが、数億年の侵食のあとです。岩盤が露出した丘は高地のひとつの特徴です。その周りの湿地が水田で、背景は高地に残存している森林地帯です。 この高原の森林には、現在生きているレムール類としては最大のインドリがすんでいます。このサルの体重は十キロ弱ですが、緑の目をもち、木の芽を食べ、両足で幹を蹴って跳びます。赤ちゃん、飛ぶインドリ。 しかし、かつては、と言ってもせいぜい400年前には、体重200キロのアーケオインドリや体重60キロのメガラダピス、パレオプロピテクスなどがすんでいました。子牛の大きさといわれるメガラダピスとは桁がちがいますが、体重一キロ程度の小型の親戚は現存していて、イタチキツネザルと呼ばれています。これは1980年代になってはじめて独立の科だと認められました。科は分類上大きなグループを示すので、これが加わっても霊長目では十五科しかありません。新しい科という大きなグループが霊長類に加わったのですから、多くの霊長類学者はびっくりしたのです。しかし、そうなってみると当たり前で、この可愛い動物にはうわ顎の切歯がなく、つまり牛などと同じ歯の形をしています。当然、これは植物食で、しかも完全に成長しきった葉を主食にするというとんでもない動物たちでした。 現存するレムール類でまちがいなくとんでもない形をしているのは、アイアイ科のアイアイですが、そのほかにもいろいろいます。 ヴェローシファカは横っ飛びで有名ですが、本来は空中を飛ぶのです。背中に赤ん坊を背負っています。これはインドリ科です。 朝起きると太陽に向かって日向ぼっこをするワオキツネザル。竹を主食にする三種のサルたち。ハイイロジェントルキツネザル、1980年代に発見されたキンイロジェントルキツネザル、そしてこの仲間の最大種、と言っても二キロですが、ヒロバナジェントルキツネザルです。これは竹の幹をばりばりワシャワシャと噛み砕いて食べて、糞は竹が粉々になったペレット状です。 オスとメスでまったく色が違うクロキツネザル、マダガスカル北端でひっそりと生きているカンムリキツネザル、これは実におとなしい性格のサルです。 西部のほんの狭い地域にしか分布しないマングースキツネザルなどが、キツネザル科の一員です。 マダガスカルのレムール類のおどろきは小型種にもあります。コビトキツネザル科には九ヶ月も乾燥季に休眠するコビトキツネザルいます。これは尾っぽに体重とおなじだけの重さの脂肪を貯めて休眠するのです。 世界最小のサル、ネズミキツネザルの仲間は全部で八種もいます。東部の熱帯雨林のやぶにすむブラウンネズミキツネザル、最近発見されたラヴェロベネズミキツネザル、そして、文字通り世界最小種30グラムのベルテネズミキツネザル。 ネズミキツネザルたちは昆虫食で、それぞれ違った昆虫を食べるのですが、これがより小さくなったのが小型コウモリではないか、と私は思っています。昆虫を捕まえるために、ついに空に飛び出したのだと。 マダガスカルには絶滅したものを含めると七科五十八種のレムール類がいます(うち絶滅2科17種)。 アイアイなどの希少生物の保護のために、マダガスカル北西部で一昨年総合調査をしました。その調査基地です。北西部のマナサムディ山地にはアイアイやヴェローシファカの最北の亜種やブラウンキツネザルの乾燥地帯亜種がいる森が残っています。ここにはマダガスカルトキやマダガスカルピューマ、吸盤をもつサラモチコウモリといった絶滅危惧種がまとまってすんでいるのです。去年10月に保護区が発足し、今年3月からマダガスカルアイアイ・ファンドと私たちで管理をするようになりました。 保護区は南北三十一キロ、この長さは東京―横浜間、大阪―神戸間、下関―宇部間に匹敵します。その中央から南を見晴らしてマナサムディ山頂を見たところです。この斜面の左下にさっきの調査基地があります。おなじ場所から保護区の北部を見たところです。保護区は面積一万四千三百八十ヘクタール、つまり下関市全体の面積の64パーセントです。地平線のむこうまで、この森は続いています。それをこれからずっと、百年とか千年の単位で守ろうというわけです。皆さんの協力をお願いします。 ええ、冗談ではなく、君たちのうちから、この保護区を10年後に私から引き継いで調査、研究と保護管理をやってやろうという人が現れるのを、私は待っています。 (ここでアイアイのビデオ) アイアイは人間が箸を使うまでに進化した時間の中で、自分の指を箸に変えてしまったのだと、言ってもよいのです。 さて、アイアイの歯と指の秘密を私たちは垣間見ました。その秘密とはアイアイの特別な形は主食に関係しているということでした。なんだ、当たり前じゃないか、と思うでしょう。まったく当たり前なのです。動物の形がいつも食べるものと関係しているのは当たり前です。しかし、そこに秘密があるのです。 私はこのアイデアにE=MC2をみつけたアインシュタインと同じくらい興奮したのです。このためにE=MH2、つまりエコロジカル・ニッチはマウス(口)と二本のハンド(手)に対応するという論文を作って、国際学会で発表したほどです。この興奮がほんものかどうか、八月末には中公新書から「親指はなぜ太いのかー直立二足歩行の起原を解く」という本が出ますから、皆さんが自分で考えてみてください。 私がアイアイの食物を調べるだけにとどまらず、そこから人類の直立二足歩行の起原を説明しようとするに至るのは、たぶんそれなりの背景があるのでしょうが、それを自分なりに遡ると、どうも西高時代に至りつきます。 それを一言で言うと、「青春の取り返しはつかんぞ」ということなのです。去年の同窓会誌に坂本龍一さんと話をして、彼は高校生の時からこうだったんだろうな、と思ったということを書きました。人生の暮れ方に立って、しみじみと感じるのは、人は高校生の時に人格の質を決定しているのだということです。 だから、言うのです。「青春の取り返しはつかんぞ」と。 残念なことに時間がなくなりました。話したいことを原稿にまとめたものがあります。生物クラブの方に渡しておきます。フロッピーですから、打ち出して、配るもよし、ということにしましょう。 (以下、フロッピーの原稿) ■青春の取り返しはつかんぞ 去年、文化祭で私の本を参考にアイアイの展示があったので、西高の卒業生には変なのがいると分かったという。それで、同窓会の会長から何か書けと言われたときに、私の頭に浮かんだのは『青春の三歳夢の裡に過ぐ』という私が西高の卒業アルバムのために作った詩のようなものだった。それは『前途遼遠、前途遼遠』という言葉に終わる原稿だったが、それが西高を三年間いて卒業するときの本当の気持ちだった。西高を卒業するとき、なんて未来は遠い先にあるのだろう、と本当に思っていた。 しかし、この年齢になると、人生はあと数十年か数年か、いずれにしてもすぐに終わる。今、「なるほど人生はこういうふうに暮れてゆくのだなあ」と実感している。人生は始まり、そして暮れてゆく。そして君たちの人生は今、ここから始まっている。だから、一言だけ言っておきたい。「青春の取り返しはつかんぞ」と。 同窓会の文章の中で、坂本龍一という音楽家と知合いだということを書いた。彼とは2000年の七月にアフリカで出会って以来だから、知り合ってまだ四年にしかならない。友人としては一番新しい。けれども、今では一番よく話す相手で、また一番よく理解してくれる。私には彼の音楽はまったく分からないが。彼は知っている人は知っているというくらい有名なミュージシャンで、ニューヨークに住んでいるので、話すといってもメールがほとんどだけれど、反応は非常に速い。2001年の夏に彼がコンサートで日本に来たので、会って、そのすぐあとに9月11日の世界貿易センタービルのテロ事件があったので、私たちは人間についてそうとう深いところまで話すようになった。 2002年4月には二回、彼とトークショーをやることになり、そのうちの一回は、横浜桐蔭学園でやった。その印象があまりに強かったので、同窓会誌にそのときのことを書いた。 このトークショーでいちばん印象に残ったのは、なんといっても坂本さんの演奏だった。桐蔭学園の講堂は二千人入るホールで、音響効果もミュージックホール並で、練習時間があるというので、坂本さんの練習をたったひとりで聞いた。私には坂本音楽はまったく分からないが、その時はなんという贅沢だろうと、しみじみ思った。とにかく、音楽を生で聞くというのは、まったく違うものだ。 彼が高校生の時と同じ目をして私に話を聞こうとするということを書いたが、彼と話をすると、彼がずっと変らずにまじめに物を考えているということが分かる。彼の性格は、高校時代にはもう形づくられている。 法隆寺や薬師寺の再建を指導した西岡常一という宮大工の棟梁は、職人というものについてこう言っている。この言葉はなぜか、長い間私の心に残っていた。 「いい職人になるにはやっぱり15か16ぐらいからです。高等学校出てからでは遅いんです。ほんとうは小学校から預かりたいですな」という一文である(西岡常一、木に学べ、小学館)。 彼はまた、これからは「役人だとか、学者だとか、そうした人が修理の指示なんかをやるんでしょう」と棟梁の時代の終わりを見ている。つまり、体で覚えた技術から頭で知った知識が優越する時代だと見ている。だが、やっぱり15か16ぐらい、というのは、この棟梁のような体に技術を覚えこませる時代の教育の方法なのだ、と思ってはいけない。 同じ年齢のことが、津本陽という小説家の「柳生兵庫助」第六巻(文春文庫、全八巻だが)に描かれている。 「流儀を身につけるには、五、六歳から稽古をはじめるのがよかった。十五歳といえば、技が自然に身に覚えこめるか否かの、きわどい境いめであった」と。十五歳はきわどい境目である。たとえば、戦国時代なら、十四歳というのはすでに元服の歳であり、成人の一端に加えられるし、上杉謙信はその歳で一群の武士を率いて初陣に勝利している。十五、六歳というのは五、六歳で目覚め始めた己自身が、開花しようとする年齢である。自分に何が適しているのか、自分の才能はどこにあるのか、それを見つけるときである。 私は人生の暮れ方に佇んでいるので、同級生たちがかつての秀才も鈍才も、高級公務員も宿無しも、皆どういう経歴をたどって、どういう結末になっているかをほぼ知ることができる。なるほど人生とはこういう流れかたをするのか、とある程度の蓋然性を持って言うことができる。 私たちは皆、高校時代までに人格の基礎を作るので、そこから大きな変化はない。だから、同級生に会うのは、いつも懐かしいのかもしれない。 「青春のとりかえしはつかんぞ」というのは、そこにある。 ■好きということ その青春の最大の意味は、自分の適性、自分の好きを見つけることだ、と私は思う。私は本を書くことを現在のなりわいとしているので、それを少し。 本を一冊まとめるためには、四百字詰め原稿用紙で大体三百枚が目安である。これを実際に書いてみるといいが、五十枚くらいで最初の挫折が来る。夏目漱石はそのあたりを「最初はうすい粥をかき回しているようなもので何の手がかりもない」と表現している。先行きの果てしなさにうんざりしてくる。そこを突き抜けるために、それぞれの物書きは苦労しているのだろうが、結局、それは「文章を書くのが好き」という一点につきる。どんどん書いてゆく。それが形になる。「自分ながらうまく表現したものだ」と自分を褒めて、「しかし、ここはリズムをそろえるべきところだ」と激励して、行き先が次第に明らかになってくるのを見る。私の場合はアイデアがわいてきた時には、かまわずにどんどん書いてしまうことにしている。そして後で削る。削って削って、これ以上削るところはない、というところまできて、ようやく整える。 それは原木を切り出すところから始まる彫刻のようなものだと、いつも思っている。原木を林切り出す作業は、日誌、ノート、写真、ビデオ、記録、論文という日常の活動とその記録と原資料である。この日常の記録活動は詳細であればあるだけよく、資料は原資料であればあるだけよい。だから、学術論文は原語でなくてはならず、原論文でなくてはならない。それを積み上げる作業が先行する。 そこから原木を選ぶ。選んだ原木の枝葉を切り始めると、それが構想となる。いよいよ原木を刻み始める。それが文章を書くことにつながる。できるだけ大雑把に原木を刻む。構想が形となるように、その木の中にある仏というものが、それは本質ということかもしれないが、どうすれば現れるかということだから、できるだけとらわれないようにする。どこまで構想が広がるか、分からないからだ。 この段階では、いつも失敗する。えらそうなことを考えすぎる。しかし、この失敗を超えて進むことが必要で、自分ながらあまりに誇大妄想である、と訂正しなければならなくても、どんどん進め、構想を確定する。その構想はできるだけ単純なほうがいい。 私にとっては原木を刻む、文章を書くという作業と、構想の核心部分を明らかにする作業は同時である。その間に、「ああ、これだ」という感覚が生まれる。そこまでに百枚は来ている。そこで新しく構想を練り直す。この段階で初めて目次が形になる。原木から大きな形が切り出される。こうなるともう材木ではない。私の物になる。芸術品とまでは言えないが、自分にとってもう切り離せないものになる。これが自分だ、いいも悪いもこれができてから言ってくれ、という気分になる。 この段階で、彫刻の手や足や頭になる部分をあちこちから刻み始める。今日は手が完成した。でも、指の形があれではなあ、と思ったりする。でも、手が完成したのは大きい、と自分を鼓舞する。あまり一度に根を詰めるとあとで反動がある。仕事となると時間に追われるが、時間だけに気を取られると、作品全体をしぼませてしまう。 亡くなった近藤四郎先生は「本は急いで書くものではありません」と「私は新書を二週間で書きましたよ。一気に書いてしまうものです」と言ったあとに言われた。それはどちらも正しいということがある。一気に書いて、書き抜いて、それを充分な時間で推敲することが大切だと私は思っている。 私の知合いの絵描きは一週間に一日、モデルのデッサンだけで過ごすが、五分で一枚の割合でデッサンを仕上げるという。 「自分の思ったとおりの線がいつでも出せるように動く腕がないと、どんな作品でも決めのたったひとつの線が描けずに絵が完成しないのです」 それは自分のリズムを完成するということだと、私は思っている。文章と彫刻の類比から言えば、手を描く、手を刻むというときに、その手はだれのものでもない、自分のリズムで刻み、描かれていないと、完成しない。完成しないと自分のものではない。 しかし、書き続けていて第二の挫折に至る。すでに書き始めてから長い時間がたっている。手と足がアンバランスになり、文章のあちこちに統一性がなくなり、生み出されたもの同士が争う状態になっている。これらに統一を与える作業は、最初の構想がどれほどしっかりしたものだったかによって決まる。それは単純な目的を追い求めるものであるほうがいい。そこへ向かって一切の形が収斂してゆくというほうがいい。ある場合は、せっかく生み出しても、木屑として捨ててしまうほうがいい。 私はけちだから、これらは作品の外伝として、「雑」とファイルに書いて、しまっておく。時には、役立つアイデアのかけらがそこに生まれていることがあるからである。 その大鉈を振うために、ここからは自分を作品の創作者としての外に置く。編集者として全体のバランスを見る。そして冷酷な評価をする。どんなに気に入っていても、全体のバランスを崩すこの手はいらない、と。何が言いたいのか、何を伝えたいのか、そこだけに絞りきる。もっと言うべきことがあるか、これでは伝わらないのではないか、と。 第二の挫折はこうして乗り切る。そうすると、完成品の姿がようやく見えるようになる。仏のお顔が原木の中から仄見えるようになる。 しかし、第三の挫折は続いて起こる。量が足りない。完成するために必要な資材の不足である。ここが境目になる。 この境目もまた、越えることができるのは、「文章を書くのが好き」という原初のエネルギーになる。この境界を軽々と超えて、三百枚の原稿を六百枚まで簡単に書き抜けるとき、原木から彫りだした「自分だけの仏のみ姿」つまり「自分にしかない作品の本質」が明らかになる。ここまでくれば、完成まであと少し。しかし、「神は細部に宿る」。もっと削れる言葉はないか、もっと簡潔にできないかと、指先ひとつおろそかにしない。 そこまで行って、初めて完成である。 ■下手くそ力 「はじめ器用な人はどんどん前へ進んでいくんですが、本当のものをつかまないうちに進んでしまうこともあるわけです。だけれども、不器用な人はとことんやらないと得心ができない。こんな人が大器晩成ですな」(西岡常一、前掲) 版画家の棟方志功。彼はヴェニスのビエンナーレで大賞を貰って日本での評価があがり、文化勲章に至った人だが、彼が晩年に言っていることがある。 「私の絵はへたくそなんですよ。絵は上手じゃない。しかし、上手にも上手クソということがある。それよりその下手くそなところが私ということです」 彼一流の言い方である。先日、東京のデパートで彼の生誕百年を記念して、倉敷の大原美術館の棟方館から出された展示会があった。そこで、この絵の下手な版画家の天才にびっくりしたことがある。それは双曲の屏風でふたつともに赤い鯉で埋め尽くされていた。片方は錦鯉にするとか、ちょっとは黒い鯉も混ぜるとか、そういうものじゃない。ただひたすらに赤い鯉が跳ね、踊り、狂っている。それは、芸術というものはこういうものだということを残りなく示していた。生命の奔流を形にしたものが芸術であり、それは整った形を見せる装飾とはまったく違ったものだ。その根底の生命力の表現能力のところで、彼は芸術家だった。その芸術は何世紀も生き延びるだけでなく、人間という種が持つ美的感覚の極限なので、ラスコーの洞窟壁画と同じように数万年という時の評価にも充分耐えるものなのだった。 それがその人にしかない「下手くその力」というものである。 誰もが芸術家ではない。誰もがそうなれるわけではない。確かに、そうだ。それは手の器用さの違い、ある種の感覚の違い、発想の豊かさの違い、そして生まれた環境の力の違い、そういうところがある。しかし、それが芸術だと分かる心は、誰もが持っているという不思議さがある。それを感得することができるように心を磨くことは誰にもできるという不思議さがある。 誰もがプロの運動選手になれるわけではない。もって生まれたものは隠しようがない。体力、筋力、運動神経能力、それらは個々人でまったく違う。そういう不公平なところがある。同等ではまったくない。しかし、自分の体の極限を極めることは、誰にもできるという不思議さがある。自分の体なのに、それが変ってゆくという不思議さを体感し、それを磨くことは、誰にもできるという不思議さがある。 自然科学の世界で言えば、世界の先端の研究は誰にでもできることではない。しかし、科学を理解する心は培うことができるという不思議がある。 誰でも自分そのものに向き合って自分その人にしかない才能を発見できれば、世界の第一線と対等に立ち向かうことができる。 ただし、そのためにはそれぞれの一級品を現物で見る、体得するという経験が必要になる。だから、現物に出会うためにむきになる必要がある。だから、展覧会でも、美術館、博物館、演奏会でも講演会でも、なんでも利用する気にならないといけない。 ■自分だけの才能を発掘する 先日、二十年ぶりに知合いに会ったが、彼は温泉評論家というものになっていた。温泉が好きなのである。どこで好きが役にたつか分からない。ブラジルのリオデジャネイロにコカパカバーナという砂浜がある。そこで七十七歳の老人が早朝から働いている。ビーチバレーのネットを編んでいる。ネット編みの名手で、ビーチバレーでブラジルがオリンピックで優勝した陰の立役者だという。バレーの世界選手権なら分かる。ビーチバレーのようなものがどうして、と思うのは、遊びこそ人生であるという哲理を知らないものの発想である。しかし、その遊びの世界にもネットを編んで世界選手権に貢献するものもいる。人間どこで何が能力か分からない。 その自分にしかない能力を見つけ出すためには、常に肯定的な精神が必要である。「お前は世界一」と言い聞かせる能力が必要である。そういう精神を培うためには、自分を自分で鍛える訓練がいる。それを探し当てるのが、青春期なのだ。だから、「若いときの苦労は買ってでもしろ」という諺がある。老年になって苦労すると、それだけでめげてしまう。老年に苦労をさせてはいけない。 しかし、青年期には苦労が絶対に必要である。自分の限定していた能力を超える経験によって、それを超えることで、精神が肯定的であるという意味が分かり、そういう精神をもつ訓練を自分にすることができる。逆に、甘やかされて青春期を過ごすと、打たれることに弱くなって、結局は自分の能力を最大限に生かすことができない。 もっとも、それを語って分かる相手というのもあって、西高生徒なら、中学校の間に、苦しい受験勉強の経験があるから、がんばるという意味とその成果について共有できるということがある。そして、自分にとって一番座りやすい場所を見出すのである。それが温泉だったり、ビーチバレーだったりすると、ちょっと恥ずかしいなあというところはある。だが、自分にとっていちばんいごこちのいい場所を苦闘のすえに見出したとしたら、誰にもはばかることはない。それが自分の天性なのである。 そして、どんな領域でも自分にしかできない、自分のかわりは世界にいない、という領域を自分で納得できたら、それが最高である。 ■文化伝統 だが、問題は残っている。これらの一切は、それをはぐくむ社会が前提になっているという点である。それは文化伝統という問題である。文化伝統は一朝にしてはできない。「天下第一関」と書かれた大額を毎日見上げている世界と、通勤ラッシュに混じって灰色の校門をくぐる生活の世界とは、まったく違う。かつて第二次世界大戦を指導したイギリスのチャーチル首相はある海戦を前に「軍艦は失うだろう。それは怖い。だが、イギリス海軍の伝統を失うことのほうが遥かに怖い。軍艦を建造するには三年かかるが、伝統を再建するためには三百年かかる」と語ったことがある。 私たちは「西高はちがう」と叩き込まれた。「他の高校が日本史から始めるのに、西高は世界史から始める。西高は違うのだ」と。それは世界史の先生だったから、そう言ったのだろうが、私たちはなにしろ素直なものだから、そのままに信じ込んだ。だが、それは本当なのだ。君たちは普通の高校生ではない。全国にさまざまな高校生がいるが、その中には桐蔭学園のような進学校もあるが、恐れることはない。下関西高なのだ。それは世界で通用するのだという気概が「天下第一関」に込められている。確かに違うのだ。東京の秀才たちとはまったく違う気迫、気魂がある。 なぜ、そうなのか。それが伝統である。 私は日本の伝統文化を維持することなしに、日本の文化的なアイデンティティーはないと信じている点で、日本主義者であると言ってもいい。それはまた「天下第一関」主義者である、と考えていただいてもいい。 笑いごとではない。東大の天文学科の主任教授は岡村さんという西高出身者だが、彼が新入生に聞く最初の言葉は「高校はどこか?」である。彼にとっては下関西高が世界で一番なので、そこから灘だのラサールだのが順位づけられている。現在、そこには近藤荘平君という西高出身の若者がいるが、彼が天文学科に進学したときに、教室中は爆笑に包まれたという。「ついに教授が年来言っていた世界一が現れた」と。 よろしいか。これが西高の伝統である。自分の価値を信じていない者に、自分の価値を生み出すことはできない。誰もが一流のプロスポーツ選手になるわけではないし、歴史に名を刻む芸術家、学者、政治家、実業家になるわけではないが、その魂において同等であるという確信がなくては、どの世界でも堂々と生きていけるわけがない。そして、その確信が人を高みにあげる。その確信を掴み取るのは、青春時代しかない。その魂の同等についての確信を、自分の感覚にまで肉体化するのは、この青春時代しかない。この時代に哲学書を読まない人間は、一生それと無縁に暮す。この青春時代に名画に感動することがなければ、一生それらとは無縁になる。この時代に宗教精神の深みを感じることがなければ、それを理解する契機を失ってしまう。 ブリア・サバランが食べ物と人格について言った格言を、私流に言い直せば、こうなる。 「高校時代にあなたが読んだ本を並べてください。あなたがどんな人だか、私は言い当てることができます」 私が自分の人生に自信を持っているのは、誰にもできないことをやったということではない。自分にいちばん相応しい世界を自分で見つけることができた、という確信があるからだ。 高校時代は、自分の人格の質を作る最後の修行時代である。今、ここにある自分を越えるとき、自分の適性、自分の好きが見えてくる。なまけるんじゃないぞ。それは誰のためでもない。どこにあるか分からない、自分のほんとうの適性、「ああ、これこそ私の好きなこと」と言えるものにめぐり合うためなんだから。 語りたいことは無数にある。しかし、それはまたどこかで。そうそう、倉敷の大原美術館所蔵だが、棟方志功には「無尽蔵」という書だか、絵だから分からない書がある。この書はすごい。しかも、文字通りの無尽蔵は実にすごい。 Copyright(C)2002-2025 Nihon Ayeaye Fund. All rights reserved. |