 |
|
NAFとは
ごあいさつ
活動報告
保護区紹介
ご寄附・お問合せ ギャラリー トピックス 関連書籍 リンク |
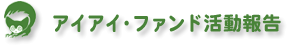 【No.29 平成22年5月】 「孫から学んだこと」
日本アイアイ・ファンド代表 1 なぜ、孫を観察しようと思ったか? 2 新発見。 3 両親と祖父母とまわりの大人。 4 心と大きな木 ―小学生の孫を見て― 1 なぜ、孫を観察しようと思ったか?  この1月に『孫の力』という本を出しました。私の11冊目の本になります。これは、私の孫娘の発育をまとめたもので、生れてすぐの赤ちゃんの時から、保育園の年長さんになった六歳までの六年間の記録です。もっとも、私は幼児の研究者というわけではありません。 この1月に『孫の力』という本を出しました。私の11冊目の本になります。これは、私の孫娘の発育をまとめたもので、生れてすぐの赤ちゃんの時から、保育園の年長さんになった六歳までの六年間の記録です。もっとも、私は幼児の研究者というわけではありません。学生時代からずっと、私は野生のサルの研究をしてきました。二十代の半ばから四十代までは房総半島のニホンザルを中心に、下北半島から屋久島まで、全国各地のニホンザルを調べて山の中を歩いていました。また、三十代の半ばからはマダガスカルにすむ特別なサル、アイアイを研究してきました。一九八四年に初めて野生のアイアイを観察して以来、マダガスカルのサルの研究をしていますが、還暦を越えた現在もマダガスカルの北西部に作ったアイアイの自然保護区の保護と管理を続けています。つまりは、生涯かけてサルを研究してきた者です。 それが「なぜ、孫の観察を?」と思われるでしょう。 「つまりは、サル学者も年老いて、ぼけて孫自慢になったのか?」とも思われるでしょうが、私としてはそういうつもりはありません。 実は、サルの研究を続けてきて、サルの一種である人間がとても不思議な生き物であることを痛感するようになった、ということがあります。マダガスカルだけでも百種を越えるサルがいて、そのどのひとつを取っても、生命の不思議さは驚くばかりです。しかし、その中でも人間は殊更に特別だと思うようになりました。ことにその心ばかりは、特別ともなんともいいようのないもので、サルの研究の最後にはこの問題に行き着くのかと思うようになりました。 もうひとつ、心が作られる幼年時代をこの目で見てみたいという動機がありました。私は中学一年生の時以来、日記をつけているので、私の心がたどった跡は記録に残されています。だから、ひとりの男の子が思春期を迎え、大人になり、老人になるという心の記録は、たった一人分とはいえ、また決して公にすることのない記録ですが、私の手元に残されています。 自分の小学生時代については、おぼろげながらいろいろな記憶があり、こんなことをした、あんな遊びもあったとたどることができます。しかし、小学校に入る前のまでの六年間については、ほとんど記憶らしいものがありません。生まれてから五、六年間の時代にこそ、人の心の基礎が作られるのでしょうが、その幼い時代について、自分自身の記憶がないのです。その頃の自分の心が見えないのは、自分の心の中に、何か不確かな部分が残っているようで、ずっと気になっていました。 人の心がどのように生まれて来るのかをはっきり見てみたいという気持ちは、サルの研究をひとまとめする頃からどんどん強くなっていました。 私たち夫婦は四十代から五十代の前半にかけて、足かけ九年、実質六年間、マダガスカルで生活をしました。その間に、マダガスカルの動物園ではアイアイの繁殖に成功し、上野動物園にアイアイやジェントルキツネザルやマダガスカルトキを送り、最初の本も出すことができました。つまり、マダガスカルでの長期の生活を終えた時は、サルの研究にも一区切りがついたところでした。 運のいいことに、私たち夫婦が長いマダガスカル生活を終えて帰国してすぐに、ほんとうに一カ月もたたないうちに孫が生まれました。しかも適当に距離のある近所に住んでくれたので、適度な間隔を保って、孫とつきあうことができました。 親たちは自分たちの手だけで赤ん坊を育てると宣言したけれど、孫が生れて2カ月で、両親は赤ん坊の面倒を見ることに疲れ果てました。今の親たちは初産年齢が三十歳前後になるので、何日もの徹夜には耐えられないのです。まして、病気にでもなったら、まったくお手上げです。それ以来、短い間隔では三日に一回、間があいても一カ月に一回、平均して1週間に一回のペースで、孫を一泊させて、面倒を見ることになりました。 観察計画があると言っても、実際には記録をその場でつけることはできません。その日の終わりに、日誌の形で、孫の行動記録を書いておきました。ところが、それでも記憶に欠落や誤りがあります。そこで、その日に、孫がこんなことをした、とか、こんなことを言ったとか、夫婦で話をすることにしました。それは、楽しみであると同時に、観察した事柄を確認する点で、役に立ちました。今ではビデオという便利なものがあるので、記憶をビデオで確認することも、細かい動作や言葉なども詳しく記録することができました。ビデオの撮影時間は6年間で55時間にもなりました。 孫の観察をするために、孫の面倒を見ることを生活の優先事項にするという原則も作っておきました。そうしないと、祖父母にもいろいろと用事があって、観察をなまけてしまうのです。さらに、孫が興味を持つ限りは、こちらの都合でそれを遮らず、止めさせず、繰り返しにも最後まで付き合うという覚悟が必要でした。これは、実は、観察のための大切な条件なのですが、祖父母でなくてはできないことでもありました。 子どもを育てることは、親であるなら誰でもやったことですが、子どもの詳しい観察は育てている間では、とうていできません。わが身を振り返っても、二十代後半から三十代前半のあの年齢では、生活を成り立たせるほうが大変でした。子どもとはたまに付き合うのが精一杯で、その行動の記録をすることなどは、とうてい思いもよりませんでした。ましてや、その子がどんなふうに心を発展させているのか、など、思いつくことさえなかったのです。 赤ちゃんの心の記録は、とてもすばらしいものでした。そのすばらしさを表現する言葉を私は持っていないので、ラフカディオ・ハーンの「日本での初めての日」という短編の冒頭の一文を紹介したいと思います。 「ぜひとも早い機会に、第一印象を書き留めておいたらいい。・・・何しろ、最初の印象なぞ、たちまちに消えてしまう。しかも一度消えたら最後、二度と戻ってきはしない。今後この国でいろんな不思議な経験をすることになるだろうが、この初めての印象ほど魅力に富んだものではない」 親や祖父母は、赤ん坊の笑顔やしぐさをいつまでも心に刻んでいるものですが、初めての印象を書き留めておくことは、なかなかできないものです。赤ん坊は毎日毎日成長し、まったく新しい世界を開いているのですが、それを見ている側の親や祖父母は、毎日新しい国を経験しているようなものです。その印象をできるだけ、書き留めようとして、六年間がたちました。 それは、実に思いも寄らない、実に面白い楽しいことばかりでした。さて、そのうちのいくつをお話できるでしょうか? 2 新発見 『孫の力』という本をまとめて、人間の赤ん坊がその心をどんな風に作っているのかを目の当たりにしました。それは、驚きの連続、新発見の連続でした。 たくさんのことが起こりました。なにしろ、六年間ですから、人の心が生まれてくる時のことですから、たくさんの事件があるのも当然です。その中でも特に印象に残ったことをお話したいと思います。 第一は、なんと言っても赤ちゃんの最初の「ほほえみ」です。赤ちゃんは生まれた時から、気持ちのよい時には笑顔を見せるのですが、親やまわりの人の声や笑顔に反応して「ほほえむ」のは、生後二〜三カ月くらいで始まります。これは、「社会的な笑い」と呼ばれています。 孫が生まれたのは、9月11日の衝撃的なテロルがあった年で、音楽家の坂本龍一さんから、彼が編集している『祈りのがれき』に何か書くように連絡があり、私は赤ん坊の最初の「ほおえみ」がもつ「神聖な意味」について書き送りました。親なら誰でも経験するこの赤ん坊の笑顔は、祖父母にとっては、また特別な意味を持つということでもあったのでしょう。「神聖な」とか、言い方がとても大げさになったのです。坂本さんに送った文章はこんなものでした。 「赤ん坊の笑顔とは何か?それはこう語っているのではないでしょうか? 『私の喜びはあなたの献身からうまれたのだから、私はあなたへ同じ喜びで必ず報いる』と。 赤ん坊に心が生まれる時、それはかげりのない「ほおえみ」として、まるで神仏の言葉のようにはるかに高いところから、人の心の中に落ちてきます。この子の笑顔が私の生きる意味なのだ、と。世界史を変えるのは、たぶんこの笑顔なのだと。」 今、読み直してみると、「大げさだな」と思いますが、その時に心底からそう思ったのだから、仕方ありません。 生後1週間で歩き出し、3週目には赤ん坊同士で遊び始めるニホンザルをずっと見てきたサル学者としては、生れて三カ月たっても歩くどころか、寝返りもやっとという人間の赤ん坊の無力さには驚かされました。 「こんな無力な生き物がどうして生き残れたのだろう?」と私は何度も思いました。しかも、理由もなく泣き出すと抱き上げて歩いていないと、なかなか眠ってくれないのですから、赤ん坊を育てることはたいへんな労力です。その大変さを越えて、無力な人の赤ん坊を育てる気持ちにさせるものは、何だろう?その答えを、この最初の笑顔に、私は「見た」と思いました。 またしても、大げさですが、その時の気持ちはこういうものでした。 「この赤ん坊のほおえみこそは、人の心の暗闇の中の灯りだ。この光を見ることこそが、人生の目的なのだ。この輝きを守りぬくことが、人生の意味なのだ」 私はそう思いました。そして、その時、私の心の中には、思春期に私に深い影響を与えた詩人ヘルダーリンの故郷に帰る時の歌『帰郷』の一節がなり響いていました。 「そうだ、これこそは生みの地、ふるさとの国の土なのだ。 おまえの探ねるものは、まぢかだ。もうおまえにまみえている」 私が孫を通して、人の心に灯りがともるのを見た瞬間だったと言ってよいと思います。 第2の発見は、「実に多様な笑い」です。赤ちゃんは最初の「ほおえみ」に始まって、「笑いをとる」ところにまで、一年たつかたたない間に一気に進みます。心が始まるのは、笑いといっしょだったのです。そして、笑いには無限の様相があり、心は無限に広がっていくのです。笑いの種類をたくさん持つことが、豊かな心なのだと、私は思うようになりました。 第3は、「遊び」でした。赤ちゃんにとっての「遊び」とは、生きていることそのもので、「遊びを食べて心は育つ」のです。心の食べ物は遊びなのでした。 第4は、赤ん坊にはまわりに大人がいることが不可欠だということでした。これは衝撃と言ってもいいものでした。なぜなら、ニホンザルの赤ん坊は確かに大人のサルたちに守られていますが、いっしょに遊ぶのは同じ赤ん坊仲間です。この赤ん坊のサルたちの同年齢の集まりは、そのまま翌年も続き、子どものサルの同年齢のグループは、サルの群れの重要な構成要素となります。社会的な動物とはそんなものだろうと、私は思ってきました。ところが、人間は違うのです。 人の赤ちゃんは三歳になるまでは、同じ年齢の赤ちゃん同士は関係しません。保育園で見ればすぐに分かりますが、同じ場所にいても赤ちゃん同士はお互いにまったく無関心です。三歳になって初めて、子ども同士で遊ぶようになります。 最初、それを見たときには目を疑いました。人間は社会的動物の筆頭だと思ってきましたが、人間の赤ちゃんは、まわりの大人に頼って生きているのです。赤ちゃん同士には関係すらありません。ですから、まわりに大人がいることが人間の赤ちゃんの発達にとって必須の条件になります。そして、たくさんの大人がまわりにいればいるほど、赤ちゃんは安定するのです。 核家族化した現代では、赤ちゃんのまわりの大人たちの役割は保育園の保育士さんにずいぶん頼っているところがあります。その意味で、保育園の社会的な役割は非常に大きいと思います。なにしろ、次の世代が心を育む場所ですから。そういう目で保育園を、社会が評価し、支えることが必要だとも思いました。保育園の本当の意味を知ったという事も、孫を見ていて痛感したことのひとつでした。 私の孫娘は1歳の誕生日前に保育園に世話になりましたが、2歳頃には、母親がよく聞いていました。「明日、ママと遊ぶ?それとも保育園に行く?」と母親から聞かれると、孫はためらいなく「ほいくえん」と答えました。具合が悪いとき、お腹をなぜてもらうのは、保育士の「Mせんせいがいい」、と言って、母親をびっくりさせたほどでした。 それほどに、赤ちゃんの時期には、ずっと近くにいてくれて、面倒を見てくれる大人は、肉親でなくとも大切だということです。ニホンザルの赤ん坊たちとはまったく違って、人間の赤ちゃんにはまわりで見つめてくれている大人が必要なのです。その実例を見たいなら、電車の中で赤ちゃんに笑顔を見せると分かります。赤ちゃんは笑顔を返してくれるか、ジッとあなたを見つめるはずです。しかも、うれしいことに、こちらが年とっているほど、この赤ちゃんの反応は強いように思います。 次回は、赤ちゃんの心が育つ時期に大人たちが必要だということを、もう少し掘り下げてみたいと思います。 3 両親と祖父母とまわりの大人  孫が生まれてから六年間の観察をまとめた『孫の力』という本を書いている間に、自分の幼い日々の断片的な記憶の底にある何ものかに気づきました。 孫が生まれてから六年間の観察をまとめた『孫の力』という本を書いている間に、自分の幼い日々の断片的な記憶の底にある何ものかに気づきました。それは、自分にとって懐かしい風景の中には、祖父母やまわりの大人の心遣いが溶けこんでいるのだということでした。そのことをはっきり知ったのは、湯川秀樹の『自己発見』という本を読んだ時でした。湯川秀樹はこう書いています。 「私の記憶の中には、いくつかの構図がはっきりと定着しているが、(中略)それは、三、四歳ごろから十二、三歳ごろまでの十年ほどを暮らした家の庭の記憶である。」 湯川秀樹が「記憶の中に定着している構図」と呼んでいる風景の中に、祖父の姿があります。 「白いひげをはやした祖父がその向こうに立って、水をやっている。そのまた向こうに離れ座敷がある。夕食後、この離れの一室で、祖父が私に漢籍の素読をする。」 湯川秀樹は、四、五歳頃に始まったこの漢籍の素読が自分を作ったということをくり返して述べています。 「私自身の経験をつないでちょっと申しますと、四、五歳くらいからの時の記憶が残っておりますが、そのころに、これはたびたびする話でありますけれども、なにか非常にむつかしい中国の古典をいろいろ読まされた。・・・私はたいへんいやでした。子供心にも、なんでやらされるのか、何の意味があろうかと思いましたけれども、それが大分のちまで続きました。 私が申したいのは、全然わけわからずに、あとをついて読んでおったことが、そのうちの全部じゃないですが、その一部がわりあい頭に残っておって、そしていつの間にやら、その意味を理解するようになっていることです。・・・私はこれはたいへん重要なことだと思うんです。」 このように湯川秀樹は書いています。 祖父になったものなら分かることですが、見所のある孫が難しい書物を読むのに、分からないなりについてくることに感動するはずです。いやだという表情はむろん分かる。それでも教わったことについてくるのを見ると「これは!」と目を見はるはずです。「この子は、天才かもしれん。なかなか見所があると思ったが、これほどとは思わなかった」という目で、祖父は孫を見ていたはずです。その祖父の心を子どもは感じ取るのです。だから、「これはたびたびする話ですが」ということになるのでしょうし、また一番大切な「構図」と湯川秀樹が呼んでいる風景の中に祖父が白いヒゲで立っているのでしょう。 湯川秀樹が祖父から受けた教育の成果は、アインシュタインの相対性理論を湯川秀樹が語るときにはっきりします。 「大分以前から、相対的、レラタィヴということとはちがう意味で、『相待つ』というのは非常に意味の深い言葉であると思っておりました」と湯川秀樹は、中国の荘子の「相待つ」という思想を紹介します。今、日本人の何人が『荘子』を読んだことがあるでしょうか?さらに、荘子の「相い待」つをどれほど深い感覚で捉えられるでしょうか。その感覚は、幼児教育でしか基礎を作ることはできないものです。湯川秀樹がいくら「相待つ」思想の深さを語っても、私にはとうてい響きません。ただ、響かないことが残念だとは思うようになりました。 子どもを慈しむ気持ちで見ている大人が、子どもの心の発達にどれほどの役割を果たすかは、湯川秀樹がいちばんいい例のように思います。「記憶の中に定着している構図」と湯川秀樹が呼んでいる風景は、人がなぜ、家や庭や故郷の風景をなつかしく思うのかを解く鍵になります。 自分が懐かしいと思う風景には、両親や祖父母だけでなく、育ててくれ遊んでくれたまわりの大人たちの慈しみの視線が溶けこんでいます。記憶が定かではない時代の自分の心を造ってくれた人々の思い出は、懐かしい風景として心の底に沈殿しているのだと、私は思うようになりました。その風景の中で可愛がってくれた人々の事は、曖昧な記憶に隠れてしまっているけれども、その人々の自分に寄せてくれた思いが風景として残されるということなのだと思いました。 たぶん、私の孫は町の中の小さな公園のある風景を懐かしく思い出すことでしょう。そこで祖父母とどんなふうに遊んだかは覚えていなくても、心に残る風景となっていくでしょう。そういう意味でも、町の風景を守っていくということは、とても大切なことなのだと、私は思うようになりました。 祖父母の及ぼす影響は、どんな人の伝記を見てもほとんど書かれていません。どんな伝記でもその人が記憶を持つようになった時代、七歳以降が始まりです。つまり、その時から意識的な自分史が始まるからです。しかし、祖父母の記憶を持つ者にとっては、祖父母の影響が決定的だった例をいくつかあげることができます。 2008年のノーベル化学賞受賞者、下村脩博士は最近新聞のインタビューに答えて祖母の教育が自分を作ったと、語っています。今年、2月14日の読売新聞です。 「父母が満州に行っている間は、佐世保の祖母に養われていた。厳しい人で、風呂から出ると耳の後ろにあかが残っていないか調べる。『打ち首になった時にみっともない』と。自分の徹底的な研究姿勢は、この祖母のしつけの影響が大きかった」。 ここには、耳あかひとつでも、生死の問題と語る厳格な祖母の姿とそれに応えた下村博士の幼い姿がよく分かります。 また、子どもなら誰でも知っている有名な絵本「腹ぺこアオムシ」の作者エリック・カールも、『星を描いて』という絵本の後書きに自筆で書いています。 「私が小さな子どもだったころ、ドイツ人の祖母は私にこんな意味のない歌をうたいながら星をかいてくれました。 “クリ クラ ガマの足、ガチョウは、はだしであるいてる” そして、さいごの夏休みの夜、流れ星の夢をみました。さいしょの星はとおい丘のむこうの谷におちました。おちてくる星はどんどん近づいてきました。とうとうとても明るい星は私に直接ぶつかりました。でも私を傷つけることはなく、それどころか、とてもすてきで、響くような感じでした。」それは、たくさんの歌や物語を聞かせてくれたエリック・カールの祖母との心の響きあいではないでしょうか? 祖父母にとって孫はかけがえのない宝ですが、孫にとっても祖父母はかけがえのない人々のようです。それには意味がある、と私は思っています。心が育つには、お互いが信頼しあっている心が響きあうことが大切だからです。 4 心と大きな木 ―小学生の孫を見て―  私の本『孫の力』の第五章の表題は「遊びを食べて子どもは育つ」でした。「笑いは心の要素である」とも申し上げました。もうひとつの発見は、子どもの心はまわりの人の心との通わせあいによって育つ、ということです。 私の本『孫の力』の第五章の表題は「遊びを食べて子どもは育つ」でした。「笑いは心の要素である」とも申し上げました。もうひとつの発見は、子どもの心はまわりの人の心との通わせあいによって育つ、ということです。私は人の心と枝葉の茂る木との比較に心を引かれるようになりました。片や変幻極まりない形を持たないもの、片や不動と形を体現しているもの、という違いを超えて、「木と心はなんて似ているんだろう」と感嘆することがたくさんあるのです。 孫が生まれる直前に、私はマダガスカルで木を植えました。アイアイの主食になるラミーという木の種子を埋めて、芽が堅い殻を破って出てくるところから見てきたわけです。この木の仲間は日本では九州南部でも自生するのですが、熱帯やマダガスカルを代表する水辺の大木で、幹が白くまっすぐに立ってつややかな緑の葉を茂らせる実に様子のいい木です。 この木を植えて四年たったころ、最初の枝が出てきました。その枝が張る様子を見たとき、とても安心しました。たったひとつの芽だけでは、それが折れた時にはどうなるのだろうと、心配でしたが、枝が広がると、どれかひとつの芽が折れても、他が代わって伸びるから大丈夫だという安心感があります。 ちょうど同じ頃、四歳になった孫が、自分の恐怖を自分で克服するという現場に出会ったことがあります。それは、実に衝撃的な観察でしたが、それは心の枝がひとつ広がった瞬間とも言える事件でした。ここから先は、ひとつやふたつの不安や悲しみでは、決して折れたきりにならない保障が生まれたと思いました。子どもの心が広がり、豊かになる様子と木の苗の成長が、私の中でひとつの風景になった瞬間でもありました。 赤ちゃんにとっては、一日一日がまったく新しい体験であり、発見と発明が引き続くということも、孫の観察から学んだことです。それは、大人になってからの発見や発明とまったく引けをとらない大きな経験です。「なんと!人は日々、自分を越えようとする動物なのだ」と書きましたが、私にとっても発見の毎日でした。 歌を唄っている子どもの声を聞くと、その心が歌にそよいでいるのを感じます。まるで木の葉が風にそよいでいるようです。「そよぐ」という言葉には、「戦い」の「戦」を漢字として使っていますが、私はこれはまったく間違いだと思います。笹の葉が震える様子には、たしかに「戦」という漢字が使われていますが、「そよぐ」はまったく日本どくとくの言葉で、ただふるえるだけではありません。光り輝きながら揺れている風景なのです。だから、「若葉がそよぐ」と歌われるのでしょう。 ヘルダーリンの詩「あたかも祭の朝(あした)に」の中では、歌は心としっかり結びつけられています。 「お前はそれらを訊ね求めるのか。歌のなかにそれらの精神はそよぐのだ」 この詩の中で使われている「そよぐ」というドイツ語はwehenで、これは風が吹くとか、旗などが風にはためくとか、精神が行き渡っているというように使われます。言葉が、これほど大切なものだということを、改めて知ったのも、孫の観察のおかげでした。 子どもの心が意識的に取りこむ最初の歌に出会った時、私は孫の観察にひとくぎりついたと思いました。子どもの心は新しい歌をどんどんとりこんで、自分の心を造っていきます。しかし、老人になった私が分かるのは、私の心はもう新しい歌を取りこまないということです。それは30歳のころに終わっていました。それも、驚愕するような発見でしたが。 歌は、心の葉にとっての風のようなものなのでしょう。木の葉は、風の中の炭酸ガスを取りこんで自分の栄養にします。そのたとえで言えば、遊びは心がそれを食べて育つのだから、心の木の大地のようなものでしょうか?では、まわりの大人たちは?その大人の第一は母親であり、父親ですが、彼らは太陽のようなものでしょう。光を受けて木々は生長します。そのように、両親や祖父母やまわりの大人の光を受けて、子どもの心は成長するのでしょう。また、木々の生長には雨も必要ですから、祖父母らの役割は子どもの心を潤す雨のようなものかもしれません。あまり多すぎると問題ですが、雨はなくてはならない要素です。 子どもの心と木の葉のたとえから言えば、女の子の木は、花の咲く木かもしれません。男の子の木は、針葉樹のように花の目立たない木かもしれません。 女の子の心は、次々に新しい展開をして、最初の花を早いうちに咲かせ、それがどんどんたくさん咲くようになって、十歳までには目を見はるほどの若い女性になるのですが、男の子はちょっと違うようです。言ってみれば、男の子は目立たない花しかつかない針葉樹のようなもので、三歳から六歳までの変化は、女の子ほど劇的ではないようです。だから、思春期になるまで男の子はぼんやりしているように見えるかもしれません。針葉樹ですから、花はほとんど目立たないけれど、いつか巨木になっているというものかもしれません。 しかし、人の心と木との単純な比較を超えるのは、心というものの特別さです。 「人が心をつくるには、相手がいる。・・・その相手との関係の中で、相手の信号を読みとろうとする心の通わせあいの中で、心は作られる」 と、私はこの本『孫の力』の冒頭で書きました。それは、赤ん坊を産んだ母親が、見た目はぶさいくな赤ん坊を「かわいい」と感じる瞬間についてある母親が書いた文章を読んで、感じたことだったのですが、なんと、これは湯川秀樹の語った荘子の「相い待つ」ということではありませんか?子どもの心は、自分をいとおしく思っている大人の心が発する言葉を、待っているのです。その待っている同士の心が繋がったとき、初めて心が育つのではないでしょうか? 心は人格を通してだけ伝わるものです。孫をひとりの人間として見ている、それどころか、これから大きく羽ばたく頼もしい命の跡継ぎとして孫を見ている心をもった祖父母が語る話だからこそ、孫の心に直接響くのです。人の心は、自分をいとおしいと思ってくれる人の心によってだけ造られるものです。これこそが、私が孫の観察を通して知った新しい発見であり、同時に古くから誰もが知っていた真実、ではないか、と思うのです。 小学生になって自転車に乗れるようになった孫娘が、こちらがどんなに走ってもおいつかない速さで並木道を遠ざかっていくのを見ると、私たちの手の届かない未来を走っている孫娘の姿を見ているような気持ちになりました。その未来が明るいものであるように、祖父として私はひたすら祈ります。 Copyright(C)2002-2025 Nihon Ayeaye Fund. All rights reserved. |